ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/
2009年10月02日
世界アルツハイマーデー記念講演会
認知症の人と家族の会主催
150名ほどの皆様にご参加頂き
誠に有難うございました
在宅ケアマネージャーから見る認知症高齢者の課題
淑徳大学准教授結城康博先生とは認知症の人と家族の会の京都総会の記念講演会で講演され、初めてお会いしました。その際名刺交換させていただき、このたび富士市においての記念講演会に講演を依頼すると、快く承諾していただき、講演会を開くことができました。テレビでは顔なじみの先生です。ケアマネージャー時代の苦労話、生の声をお聞きすることができ、とっても良かったです。また、10/6(火)朝8:35~9:25NHK生活ほっとモーニングに生出演されます。是非ご覧になってください!
ここをクリックすると講演会の様子を大きく見ることができます
↓

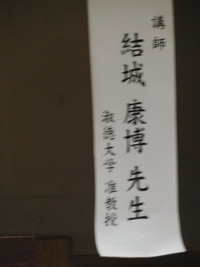














にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
150名ほどの皆様にご参加頂き
誠に有難うございました
在宅ケアマネージャーから見る認知症高齢者の課題
淑徳大学准教授結城康博先生とは認知症の人と家族の会の京都総会の記念講演会で講演され、初めてお会いしました。その際名刺交換させていただき、このたび富士市においての記念講演会に講演を依頼すると、快く承諾していただき、講演会を開くことができました。テレビでは顔なじみの先生です。ケアマネージャー時代の苦労話、生の声をお聞きすることができ、とっても良かったです。また、10/6(火)朝8:35~9:25NHK生活ほっとモーニングに生出演されます。是非ご覧になってください!

ここをクリックすると講演会の様子を大きく見ることができます
↓

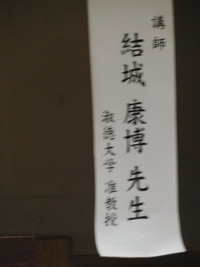














にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月02日
アルツハイマーデー結城康博先生記念講演会
世界アルツハイマーデー記念講演会
認知症の人と家族の会 静岡県支部 主催
在宅ケアマネージャーから見る認知症高齢者の課題
淑徳大学准教授 結城康
講演内容の一部より
大学准教授になる前の6年包括支援センター職員時代にケアーマネージャーとして勤務、ケアマネージャー時代の事例を通して皆さんで考えて見ましょう。
最初の事例は88歳実母、10年前まで一人暮らしをしていたが心臓発作にて手術施行をきっかけに同居。徐々に物忘れが目立ち始める。認知症の見極めが単なる物忘れで片付けるのか実母の介護にあたって悩む様子を紹介。プラスチック製の湯たんぽを火にかけたことから認知症を疑い精神科を受診した。MRIの結果アルツハイマー型認知症と診断されたが心臓病があるためアリセプトを服用できないケアーで支援している。
①.家族間と第3者で認知症の疑いをどのへんで見極めることができるのか
②.第3者が絡んで近所づきあい、火の不始末をきっかけに、心臓病を理由に専門医精神科へ受診
③.専門医へ連れて行くまで、信頼関係、人間関係が大切、精神科へのハードルは高い
④.介護保険の申請に本人が同意してくれるか
認知症の実母を介護していて、最も悩んだのは「認知症」なのか「単なる物忘れなのか」
認知症の疑いをもつ、「時間」「空間」「場所」といった認識が曖昧になる。
空間→自分の家にいると落ち着くが家族で旅行すると不安定になる。突拍子もない行動をとる。
場所→散歩に行くと帰って来れなくなる。
80~90近くなると尿漏れがあり、下着を隠してしまう。
本人のプライドを大事にしながら専門医への受診を促すことは大変であった。
よって認知症の早期発見、早期治療は簡単ではないと感じたそうである。
事例2ではゴミ屋敷の認知症問題
天涯孤独の一人暮らしの男性80代。人との関わりが嫌い、意地っ張り、全て外食で購入したものは片付けられない、週2回入浴目的でデーサービスを使うようになったが、お金がもったいないとサービスを増やすことを拒む。
クモ膜下出血で亡くなったのだが、100万の束が5つと預金通帳に5000万あった。マンション住まいであったのでお金が低所得者ではないと思っていたが、こんなのお金がある人とは思わなかった。
もし、一人でも信頼できる人間がいればこの高齢者はもっと、いい老後が送れたはずなのに!
つまりいくらお金があっても、使いかたを支援してくれる人がいなければ、いくら貯めたものでも活用できない!結局この大金は相続者がいないので、「国」へ収めることになりました。

テレビでおなじみの結城先生10/6(火)NHKテレビ
生活ほっとモーニング8:35~9:25 中尾ミエさんと生出演されま~す
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
認知症の人と家族の会 静岡県支部 主催
在宅ケアマネージャーから見る認知症高齢者の課題
淑徳大学准教授 結城康
講演内容の一部より
大学准教授になる前の6年包括支援センター職員時代にケアーマネージャーとして勤務、ケアマネージャー時代の事例を通して皆さんで考えて見ましょう。
最初の事例は88歳実母、10年前まで一人暮らしをしていたが心臓発作にて手術施行をきっかけに同居。徐々に物忘れが目立ち始める。認知症の見極めが単なる物忘れで片付けるのか実母の介護にあたって悩む様子を紹介。プラスチック製の湯たんぽを火にかけたことから認知症を疑い精神科を受診した。MRIの結果アルツハイマー型認知症と診断されたが心臓病があるためアリセプトを服用できないケアーで支援している。
①.家族間と第3者で認知症の疑いをどのへんで見極めることができるのか
②.第3者が絡んで近所づきあい、火の不始末をきっかけに、心臓病を理由に専門医精神科へ受診
③.専門医へ連れて行くまで、信頼関係、人間関係が大切、精神科へのハードルは高い
④.介護保険の申請に本人が同意してくれるか
認知症の実母を介護していて、最も悩んだのは「認知症」なのか「単なる物忘れなのか」
認知症の疑いをもつ、「時間」「空間」「場所」といった認識が曖昧になる。
空間→自分の家にいると落ち着くが家族で旅行すると不安定になる。突拍子もない行動をとる。
場所→散歩に行くと帰って来れなくなる。
80~90近くなると尿漏れがあり、下着を隠してしまう。
本人のプライドを大事にしながら専門医への受診を促すことは大変であった。
よって認知症の早期発見、早期治療は簡単ではないと感じたそうである。
事例2ではゴミ屋敷の認知症問題
天涯孤独の一人暮らしの男性80代。人との関わりが嫌い、意地っ張り、全て外食で購入したものは片付けられない、週2回入浴目的でデーサービスを使うようになったが、お金がもったいないとサービスを増やすことを拒む。
クモ膜下出血で亡くなったのだが、100万の束が5つと預金通帳に5000万あった。マンション住まいであったのでお金が低所得者ではないと思っていたが、こんなのお金がある人とは思わなかった。
もし、一人でも信頼できる人間がいればこの高齢者はもっと、いい老後が送れたはずなのに!
つまりいくらお金があっても、使いかたを支援してくれる人がいなければ、いくら貯めたものでも活用できない!結局この大金は相続者がいないので、「国」へ収めることになりました。

テレビでおなじみの結城先生10/6(火)NHKテレビ
生活ほっとモーニング8:35~9:25 中尾ミエさんと生出演されま~す
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月02日
認知症をよく理解するための8大法則 1原則 第5法則
認知症を良く理解するための
8大法則 1原則
認知症の人と家族の会副代表 杉山孝博医師
第5法則 感情残像の法則
認知症の人は、第1法則の記憶障害に関する法則が示すように、自分が話したり、聞いたり、行動したことはすぐわすれてしまいます。しかし、感情の世界はしっかる残っていて、瞬間的に目に入った光が消えた後でも残像として残るように、その人がそのときいだいた感情は相当時間続きます。このことを「感情残像の法則」といいます。出来事の事実関係は把握できないのですが、それが感情の波として残されるのです。
認知症の人の症状に気づき、医師からも認知症と診断されると、家族は認知症を少しでも軽くしたいと思い、いろいろ教えたり、詳しい説明をしたり、注意したり、叱ったりします。しかし、このような努力はほとんどの場合、効を奏しないばかりか、認知症の症状をかえって悪化させてしまうのです。
まわり(とくに一生懸命介護している人)からどんな説明を受けても、その内容はすぐに忘れてしまい、単に相手をうるさい人、いやなことを言う人、怖い人と捕らえてしまいます。つまり、自分のことをいろいろ気遣ってくれる身近な人と思わないのです。
これをどう理解したらいいでしょうか。
認知症の人は、記憶などの知的能力の低下によって、一般常識が通用する理性の世界から出てしまって、感情を支配する世界に住んでいる、と考えたらいいでしょう。
動物の世界に似た一面があります。弱肉強食の世界に住む動物たちは、相手が敵か味方か、安心して気を許せる対象か、否かを速やかに判断し、感情として表現します。認知症の人も実は同じような存在なのです。安全で友好的な世界から抜け出してしまった認知症の人は、感情を研ぎすまして生きざるをえない世界の中に置かれているのです。
周囲のものはそのような本人が穏かな気持になれるよう、心から同情の気持で接することが必要となります。つまり認知症の人を介護するときは、「説得よりも同情」です。感情が残るといっても、悪い感情ばかりが残るのではないので、よい感情が本人に残るように接することが大切です。
自分を認めてくれ優しくしてくれる相手には、本人も穏かな接触をもてるようになるものです。最初のうちは難しいかもしれませんが、「どうもありがとう。助かるわ」「そう、それは大変だね」「それはよかったね」などの言葉が言えるようになれば、その介護者は上手な介護ができているといえます。
例えば認知症の人が濡れた洗濯物を取りこんでいるのを見つけたとき「まだ乾いてないのにお母さん、どうしてわからないの、余計なことをしてくれて」というのと「ああ、お母さん手伝ってくださってありがとう。後は私がやりますからそちらで休んでいてください」というのとでは介護のしやすさが大きく違ってくるものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
8大法則 1原則
認知症の人と家族の会副代表 杉山孝博医師
第5法則 感情残像の法則
認知症の人は、第1法則の記憶障害に関する法則が示すように、自分が話したり、聞いたり、行動したことはすぐわすれてしまいます。しかし、感情の世界はしっかる残っていて、瞬間的に目に入った光が消えた後でも残像として残るように、その人がそのときいだいた感情は相当時間続きます。このことを「感情残像の法則」といいます。出来事の事実関係は把握できないのですが、それが感情の波として残されるのです。
認知症の人の症状に気づき、医師からも認知症と診断されると、家族は認知症を少しでも軽くしたいと思い、いろいろ教えたり、詳しい説明をしたり、注意したり、叱ったりします。しかし、このような努力はほとんどの場合、効を奏しないばかりか、認知症の症状をかえって悪化させてしまうのです。
まわり(とくに一生懸命介護している人)からどんな説明を受けても、その内容はすぐに忘れてしまい、単に相手をうるさい人、いやなことを言う人、怖い人と捕らえてしまいます。つまり、自分のことをいろいろ気遣ってくれる身近な人と思わないのです。
これをどう理解したらいいでしょうか。
認知症の人は、記憶などの知的能力の低下によって、一般常識が通用する理性の世界から出てしまって、感情を支配する世界に住んでいる、と考えたらいいでしょう。
動物の世界に似た一面があります。弱肉強食の世界に住む動物たちは、相手が敵か味方か、安心して気を許せる対象か、否かを速やかに判断し、感情として表現します。認知症の人も実は同じような存在なのです。安全で友好的な世界から抜け出してしまった認知症の人は、感情を研ぎすまして生きざるをえない世界の中に置かれているのです。
周囲のものはそのような本人が穏かな気持になれるよう、心から同情の気持で接することが必要となります。つまり認知症の人を介護するときは、「説得よりも同情」です。感情が残るといっても、悪い感情ばかりが残るのではないので、よい感情が本人に残るように接することが大切です。
自分を認めてくれ優しくしてくれる相手には、本人も穏かな接触をもてるようになるものです。最初のうちは難しいかもしれませんが、「どうもありがとう。助かるわ」「そう、それは大変だね」「それはよかったね」などの言葉が言えるようになれば、その介護者は上手な介護ができているといえます。
例えば認知症の人が濡れた洗濯物を取りこんでいるのを見つけたとき「まだ乾いてないのにお母さん、どうしてわからないの、余計なことをしてくれて」というのと「ああ、お母さん手伝ってくださってありがとう。後は私がやりますからそちらで休んでいてください」というのとでは介護のしやすさが大きく違ってくるものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ




