ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/
2009年10月18日
日光浴

日光浴 物干し竿につかまり運動です

夜間良く眠れるように太陽の光を一杯浴びてくださいね

外に出たら居眠りが始まりました。
いい天気で気持が良いですねー
 この天気では眠くなりますよ
この天気では眠くなりますよにほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月18日
認知症を理解する パート3
認知症を理解する パート3
(認知主サポーター養成講座標準教材より)
症状3-理解・判断力の障害
認知症になると、ものを考えることにも障害が起こります。具体的な現象で次の変化が起こります。
1.考えるスピードが遅くなる
逆の見方をするなら、時間をかければ自分なりの結論にいたることが出来ます。急がせないことが大切です。
2.二つ以上のことが重なると上手く処理できなくなる。
一度に処理できる情報の量が減ります。念を押そうと思って長々と説明すると、益々混乱します。必要な話はシンプルにに表現することが大切です。
3.些細な変化、いつもと違う出来事で混乱をきたしやすくなる。
お葬式での不自然な行動や、夫の入院で混乱してしまったことをきっかけに認知症が発覚する場合があります。予想外のことが起こったとき、補いを守ってくれる人がいれば日常生活は継続できます。
4.観念的な事柄と現実的、具体的な事柄が結びつかなくなる
「糖尿病だから食べすぎはいけないと」ということはわかっているのに、目の前のお饅頭を食べてよいのかどうか判断できない。「倹約は大切」と言いながらセールスマンの口車にのって高価な羽布団を何組も買ってしまうということが起こります。また、目に見えないメカニズムが理解できなくなるので、自動販売機や交通機関の自動改札、銀行のATMなどの前では、まごまごしてしまいます。全自動洗濯機、火が目に見えないIHクッカーなど上手く使えなくなります。
症状4-実行機能障害
計画を立てて按配することが出来なくなる
スパーマーケットで大根を見て、健康な人は冷蔵庫にあった油揚げと一緒に味噌汁を作ろうと考えます。認知症になると冷蔵庫の油揚げのことはすっかり忘れて、大根と一緒に油揚げを買ってしまいます。
ところが、あとになっていざ夕食の準備に取りかかると、さっき買ってきた大根も油揚げも頭から消えています。冷蔵庫を開けて目に入った別の野菜で味噌汁を作り、冷蔵庫に油揚げが2つと大根が残ります。こういうことが幾度となく起こり冷蔵庫には同じ食材が並びます。
認知症の人にとっては、ご飯を炊き、同時進行でおかずを作るのは至難の業です。健康な人は頭の中で計画を立て、予想外の変化にも適切に按配してスムーズに進めることが出来ます。認知症になると按配したりができなくなり、日常生活が上手く進まなくなります。
保たれている能力を活用する支援
でも、認知症の人は「何も出来ない」わけではありません。献立を考えたり、料理を並行して進めることは上手くできませんが、だれかが、全体に目を配りつつ、按配をすれば一つひとつの調理の作業は上手に出来ます。「今日の味噌汁は、大根と油揚げだよね」の一言で油揚げが冷蔵庫にたまることはありません。「炊飯器のスイッチはそろそろ入れたほうが良いかな?」と聞いてくれる人がいれば、今までどうり、食事の準備ができます。こういう援助は根気がいるし疲れますが、認知症の人にとっては必要な支援です。
こうした手助けをしてくれる人がいれば、そのさきは自分でできるということが沢山あります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
(認知主サポーター養成講座標準教材より)
症状3-理解・判断力の障害
認知症になると、ものを考えることにも障害が起こります。具体的な現象で次の変化が起こります。
1.考えるスピードが遅くなる
逆の見方をするなら、時間をかければ自分なりの結論にいたることが出来ます。急がせないことが大切です。
2.二つ以上のことが重なると上手く処理できなくなる。
一度に処理できる情報の量が減ります。念を押そうと思って長々と説明すると、益々混乱します。必要な話はシンプルにに表現することが大切です。
3.些細な変化、いつもと違う出来事で混乱をきたしやすくなる。
お葬式での不自然な行動や、夫の入院で混乱してしまったことをきっかけに認知症が発覚する場合があります。予想外のことが起こったとき、補いを守ってくれる人がいれば日常生活は継続できます。
4.観念的な事柄と現実的、具体的な事柄が結びつかなくなる
「糖尿病だから食べすぎはいけないと」ということはわかっているのに、目の前のお饅頭を食べてよいのかどうか判断できない。「倹約は大切」と言いながらセールスマンの口車にのって高価な羽布団を何組も買ってしまうということが起こります。また、目に見えないメカニズムが理解できなくなるので、自動販売機や交通機関の自動改札、銀行のATMなどの前では、まごまごしてしまいます。全自動洗濯機、火が目に見えないIHクッカーなど上手く使えなくなります。
症状4-実行機能障害
計画を立てて按配することが出来なくなる
スパーマーケットで大根を見て、健康な人は冷蔵庫にあった油揚げと一緒に味噌汁を作ろうと考えます。認知症になると冷蔵庫の油揚げのことはすっかり忘れて、大根と一緒に油揚げを買ってしまいます。
ところが、あとになっていざ夕食の準備に取りかかると、さっき買ってきた大根も油揚げも頭から消えています。冷蔵庫を開けて目に入った別の野菜で味噌汁を作り、冷蔵庫に油揚げが2つと大根が残ります。こういうことが幾度となく起こり冷蔵庫には同じ食材が並びます。
認知症の人にとっては、ご飯を炊き、同時進行でおかずを作るのは至難の業です。健康な人は頭の中で計画を立て、予想外の変化にも適切に按配してスムーズに進めることが出来ます。認知症になると按配したりができなくなり、日常生活が上手く進まなくなります。
保たれている能力を活用する支援
でも、認知症の人は「何も出来ない」わけではありません。献立を考えたり、料理を並行して進めることは上手くできませんが、だれかが、全体に目を配りつつ、按配をすれば一つひとつの調理の作業は上手に出来ます。「今日の味噌汁は、大根と油揚げだよね」の一言で油揚げが冷蔵庫にたまることはありません。「炊飯器のスイッチはそろそろ入れたほうが良いかな?」と聞いてくれる人がいれば、今までどうり、食事の準備ができます。こういう援助は根気がいるし疲れますが、認知症の人にとっては必要な支援です。
こうした手助けをしてくれる人がいれば、そのさきは自分でできるということが沢山あります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月18日
認知症を理解する パート2
認知症を理解する パート2
(認知症サポータ養成講座標準教材より)
3.中核症状
症状1ー記憶障害
人間には、目や耳のとらえた沢山の情報の中から関心のあるものを一時的にとらえておく器官(海馬、仮にイソギンチャクと呼ぶ)と、重要な情報を頭の中に長期に保存する「記憶の壷」が脳の中にあると考えてください。いったん「記憶の壷」に入れば、普段は思い出さなくても、必要なときに必要な情報を取り出すことができます。
しかし、年をとるとイソギンチャクの力が衰え、、一度に沢山の情報を捕まえておくことができなくなり、捕まえても、「壷」に移すのに手間取るようになります。「壷」の中から必要な情報を探し出すことも、時々失敗します。年をとっても
覚えが悪くなったッたり、ど忘れが増えるのはこのためです。それでもイソギンチャクの足はそれなりに機能しているので、二度三度と繰り返しているうち、大事な情報は「壷」に収まります。
ところが、認知症になると、いそぎんちゃくはの足が衰えてしまうため「壷」に収めることができなくなります。新しいことを記憶できずに、先ほど聞いたことさえ思い出せないのです。さらに、病気が進行すれば、「壷」が溶け始め、覚えていたはずの記憶も失われていきます。
症状2-見当識障害
見当識障害は、記憶障害と並んで早くから現れる障害です。
まず、時間や季節感の感覚が薄れることから
時間に関する見当識が薄らぐと、長時間待つとか、予定に合わせて準備することができなくなります。何回も年を押しておいた外出の時刻に準備ができなかったりします。もう少し進むと、時間感覚けでなく日付や季節、年次におよび、何回も今日は何日かと質問します。季節感のない服を着る、自分の年が分からないなどが起こります。
進行すると迷子になったり、遠くに歩いていこうとする
初めは方向感覚が薄らいでも、周囲の景色をヒントに道を間違えないで歩くことができますが、暗くてヒントがなくなると迷子になります。進行すると、近所で迷子になったり、夜、自宅のお手洗いの場所が分からなくなったりします。また、とうてい歩いていけそうにない距離を歩いて出かけようとします。
人間関係の見当識はかなり進行してから
過去に獲得した記憶をを失うという症状まで進行すると、自分の年齢や人の生死に関する記憶がなくなり、周囲の人との関係が分からなくなります。80歳の人が、30代以降の記憶が薄れてしまい、50歳の娘に対し、姉さん、叔母さんと呼んで家族を混乱させます。
又、とっくに亡くなった母親が心配しているからと、遠く離れた郷里の実家に歩いて帰ろうとすることもあります。
見当識とは、、現在の年月や時刻、自分がどこにいるかなど、基本的な状況を把握することをいいます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
(認知症サポータ養成講座標準教材より)
3.中核症状
症状1ー記憶障害
人間には、目や耳のとらえた沢山の情報の中から関心のあるものを一時的にとらえておく器官(海馬、仮にイソギンチャクと呼ぶ)と、重要な情報を頭の中に長期に保存する「記憶の壷」が脳の中にあると考えてください。いったん「記憶の壷」に入れば、普段は思い出さなくても、必要なときに必要な情報を取り出すことができます。
しかし、年をとるとイソギンチャクの力が衰え、、一度に沢山の情報を捕まえておくことができなくなり、捕まえても、「壷」に移すのに手間取るようになります。「壷」の中から必要な情報を探し出すことも、時々失敗します。年をとっても
覚えが悪くなったッたり、ど忘れが増えるのはこのためです。それでもイソギンチャクの足はそれなりに機能しているので、二度三度と繰り返しているうち、大事な情報は「壷」に収まります。
ところが、認知症になると、いそぎんちゃくはの足が衰えてしまうため「壷」に収めることができなくなります。新しいことを記憶できずに、先ほど聞いたことさえ思い出せないのです。さらに、病気が進行すれば、「壷」が溶け始め、覚えていたはずの記憶も失われていきます。
症状2-見当識障害
見当識障害は、記憶障害と並んで早くから現れる障害です。
まず、時間や季節感の感覚が薄れることから
時間に関する見当識が薄らぐと、長時間待つとか、予定に合わせて準備することができなくなります。何回も年を押しておいた外出の時刻に準備ができなかったりします。もう少し進むと、時間感覚けでなく日付や季節、年次におよび、何回も今日は何日かと質問します。季節感のない服を着る、自分の年が分からないなどが起こります。
進行すると迷子になったり、遠くに歩いていこうとする
初めは方向感覚が薄らいでも、周囲の景色をヒントに道を間違えないで歩くことができますが、暗くてヒントがなくなると迷子になります。進行すると、近所で迷子になったり、夜、自宅のお手洗いの場所が分からなくなったりします。また、とうてい歩いていけそうにない距離を歩いて出かけようとします。
人間関係の見当識はかなり進行してから
過去に獲得した記憶をを失うという症状まで進行すると、自分の年齢や人の生死に関する記憶がなくなり、周囲の人との関係が分からなくなります。80歳の人が、30代以降の記憶が薄れてしまい、50歳の娘に対し、姉さん、叔母さんと呼んで家族を混乱させます。
又、とっくに亡くなった母親が心配しているからと、遠く離れた郷里の実家に歩いて帰ろうとすることもあります。
見当識とは、、現在の年月や時刻、自分がどこにいるかなど、基本的な状況を把握することをいいます。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月17日
認知症を理解するパート1
認知症を理解する パート1
(認知症サポーター養成講座標準教材より)
1.認知症とはどういうものですか?
脳は、私たちのほとんどがあらゆる活動をコントロールしている司令塔です。それがうまく働かなければ、精神活動もスムーズに運ばなくなります。認知症とは色々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったためにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が得てくる状態(およそ6ヶ月以上継続)を指します。
認知症を引き起こす病気のうち、最も多いのは、脳の神経細胞がゆっくり死んでいく「変性疾患」と呼ばれる病気です。アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、レビー小体病等がこの「変性疾患」二あたります。
続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、能動脈硬化などのために、神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、その結果その部分の神経細胞が死んだり、神経のネットワークが壊れてしまう脳血管性認知症です。
2.認知症の症状ー中核症状と周辺症状
脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状が記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下、実行機能の低下などちゅうかっく症状と呼ばれるものです。これらの中核症状のため周囲で起こっている現実を正しく認識できなくなります。
本人がもともと持っている性格、環境、人間関係などさまざまな要因がからみ合って、うつ状態や妄想のような精神症状や、日常生活への適応を困難にする行動上の問題が起こってきます。。これらを周辺症状と呼ぶことがあります。
このほか認知症にはその原因となる病気によって多少の違いはあるものの、さまざまな身体的症状も出てきます。とくに血管性認知症の一部では、早い時期から麻痺などの身体症状が合併することがあります。アルツハイマー型認知症でも、振興すると』歩行がつたなくなり、終末期まで進行すれば寝たきりになってしまう人も少なくありません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
(認知症サポーター養成講座標準教材より)
1.認知症とはどういうものですか?
脳は、私たちのほとんどがあらゆる活動をコントロールしている司令塔です。それがうまく働かなければ、精神活動もスムーズに運ばなくなります。認知症とは色々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったためにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が得てくる状態(およそ6ヶ月以上継続)を指します。
認知症を引き起こす病気のうち、最も多いのは、脳の神経細胞がゆっくり死んでいく「変性疾患」と呼ばれる病気です。アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、レビー小体病等がこの「変性疾患」二あたります。
続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、能動脈硬化などのために、神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、その結果その部分の神経細胞が死んだり、神経のネットワークが壊れてしまう脳血管性認知症です。
2.認知症の症状ー中核症状と周辺症状
脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状が記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下、実行機能の低下などちゅうかっく症状と呼ばれるものです。これらの中核症状のため周囲で起こっている現実を正しく認識できなくなります。
本人がもともと持っている性格、環境、人間関係などさまざまな要因がからみ合って、うつ状態や妄想のような精神症状や、日常生活への適応を困難にする行動上の問題が起こってきます。。これらを周辺症状と呼ぶことがあります。
このほか認知症にはその原因となる病気によって多少の違いはあるものの、さまざまな身体的症状も出てきます。とくに血管性認知症の一部では、早い時期から麻痺などの身体症状が合併することがあります。アルツハイマー型認知症でも、振興すると』歩行がつたなくなり、終末期まで進行すれば寝たきりになってしまう人も少なくありません。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月17日
2人3脚の脳トレーニング
2人3脚では良くかんじの脳トレをします
皆さんも挑戦してみてくださ~い

考えることによって脳が刺激されます
99歳ですね
 こんな感じで進めていきます
こんな感じで進めていきます81歳
111歳
108歳
100歳
90歳
88歳
皆さん分かりましたか?
この機会に覚えましょう
意識して覚えようとしないと忘れてしまいます
反復練習が大切です

ここまで長生きしたいですね
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月16日
Q&A お年寄りのうつと認知症のうつのちがいは何でしょう
Q 44 お年寄りに見られるうつと認知症にみられるうつの違いを教えてください。親戚のおばさんがうつで家の中に引きこもっていることが多いのですが、認知症ではないかと思うくらい忘れっぽくなっています。
A:私たちも、日常の生活の中で体調が悪かったり、仕事がうまくいかなくなると、憂うつな気持ちになりますが、普通なら1~2日くらいで気分は元にに戻ってきます。それに対してうつ気分が1週間も2週間も続くのがうつ病です。うつ病はもともと認知機能の病気ではなく、感情の病気です。うつ病の症状には①.うつ気分②.意欲の低下③.身体的症状に分けられます。
(長谷川和夫 認知症知りたいことガイドブックより)
第1は、うつ気分です。何をしても面白くない。不安で淋しい。そして、暗い気持ちが続いて悲観的な思いにとらわれ死にたくなります。第2は、意欲の低下です。何事にもやる気をなくして、おっくうになります。注意力が低下するとともに、考えもまとまらず、決めることが難しくなります。その状態はまるで認知症のように見えてしまいます。第3は、身体的な症状です。頭痛や頭重感、肩こり、不眠、食欲不振、便秘などが起こり、体重も減ってきます。ただし、これらの3つの症状は、常に全部あるわけではなく、個人差や経過によっても変わります。
うつ病が治ると、この認知症に似た症状は消失するため、それを一過性の認知症とか仮性認知症とかいいます。この仮性認知症と本物の認知症とを間違えないようにしないと大変です。うつ病の場合は生きていくことに空しさを感じ、死にたくなって、自殺する可能性があります。しかもうつ病は抗うつ薬等の薬物療法で直すことができるのですから、この両者をきちんと判別することが重要です。
仮性認知症と本物の認知症を見分けるポイント
うつ病の場合は、口数が少なく、日常の生活において行動量が少なくなり、外出や人に合うことを避けるようになります。また、悲観的で愚痴っぽくなり、「あんなことをしなければよかった」などと自分を責めたり、過去のことをくよくよ悩んだりします。その他、からだの不調をやたらと訴えます。
「肩がこる」「便秘がひどい」「疲れやすい」「眠れない」「胃腸の具合が悪い」「食欲がない」などと、暗い表情をしてくどくどとぼそぼそ繰り返すのが特徴です。
それに対して本物の認知症の人はよく喋るし、がっくりもしていません。むしろ元気そのもので、身体の不調を訴えることもなく、「どこも悪くない」と主張します。突拍子もないことを言いますが、くどくどとは言いません。そういうところが大きく違うのです。
それにうつ病は、配偶者を亡くすとか、大切にしていた陶器を壊されたとか、かわいがっていたペットが死んだというような喪失体験(事件)に引き続いて起こるケースが多いのです。お年寄りが丹精こめて手入れしてしていた盆栽を、ある夜、酔っ払いが庭に入ってきてむちゃくちゃに壊してしまい、それをきっかけに翌日からうつ病になってしまったという例もあります。
特にお年寄りの場合、短い期間にこうした喪失体験が1つだけでなく、いくつも重なって起こることがあります。定年退職で社会的な役割を失った、身体の調子がどうも悪い、仲の良かった友人が亡くなった、老後の収入としてあてにしていたアパートの経営が不景気でうまくいかなくなった・・・。このような体験が重なり合い、それをきっかけにしてうつ状態を起こすことがしばしばあります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
A:私たちも、日常の生活の中で体調が悪かったり、仕事がうまくいかなくなると、憂うつな気持ちになりますが、普通なら1~2日くらいで気分は元にに戻ってきます。それに対してうつ気分が1週間も2週間も続くのがうつ病です。うつ病はもともと認知機能の病気ではなく、感情の病気です。うつ病の症状には①.うつ気分②.意欲の低下③.身体的症状に分けられます。
(長谷川和夫 認知症知りたいことガイドブックより)
第1は、うつ気分です。何をしても面白くない。不安で淋しい。そして、暗い気持ちが続いて悲観的な思いにとらわれ死にたくなります。第2は、意欲の低下です。何事にもやる気をなくして、おっくうになります。注意力が低下するとともに、考えもまとまらず、決めることが難しくなります。その状態はまるで認知症のように見えてしまいます。第3は、身体的な症状です。頭痛や頭重感、肩こり、不眠、食欲不振、便秘などが起こり、体重も減ってきます。ただし、これらの3つの症状は、常に全部あるわけではなく、個人差や経過によっても変わります。
うつ病が治ると、この認知症に似た症状は消失するため、それを一過性の認知症とか仮性認知症とかいいます。この仮性認知症と本物の認知症とを間違えないようにしないと大変です。うつ病の場合は生きていくことに空しさを感じ、死にたくなって、自殺する可能性があります。しかもうつ病は抗うつ薬等の薬物療法で直すことができるのですから、この両者をきちんと判別することが重要です。
仮性認知症と本物の認知症を見分けるポイント
うつ病の場合は、口数が少なく、日常の生活において行動量が少なくなり、外出や人に合うことを避けるようになります。また、悲観的で愚痴っぽくなり、「あんなことをしなければよかった」などと自分を責めたり、過去のことをくよくよ悩んだりします。その他、からだの不調をやたらと訴えます。
「肩がこる」「便秘がひどい」「疲れやすい」「眠れない」「胃腸の具合が悪い」「食欲がない」などと、暗い表情をしてくどくどとぼそぼそ繰り返すのが特徴です。
それに対して本物の認知症の人はよく喋るし、がっくりもしていません。むしろ元気そのもので、身体の不調を訴えることもなく、「どこも悪くない」と主張します。突拍子もないことを言いますが、くどくどとは言いません。そういうところが大きく違うのです。
それにうつ病は、配偶者を亡くすとか、大切にしていた陶器を壊されたとか、かわいがっていたペットが死んだというような喪失体験(事件)に引き続いて起こるケースが多いのです。お年寄りが丹精こめて手入れしてしていた盆栽を、ある夜、酔っ払いが庭に入ってきてむちゃくちゃに壊してしまい、それをきっかけに翌日からうつ病になってしまったという例もあります。
特にお年寄りの場合、短い期間にこうした喪失体験が1つだけでなく、いくつも重なって起こることがあります。定年退職で社会的な役割を失った、身体の調子がどうも悪い、仲の良かった友人が亡くなった、老後の収入としてあてにしていたアパートの経営が不景気でうまくいかなくなった・・・。このような体験が重なり合い、それをきっかけにしてうつ状態を起こすことがしばしばあります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月16日
大正琴のお稽古
Posted by 2人3脚 at
12:05
│Comments(0)
2009年10月15日
第39回富士市福祉展へ見学

第38回 富士市福祉展へGO

今日の午後利用者さん6名でロゼシアター1階展示室へ
高齢者・障害児(者)・福祉団体のみなさんが丹精こめて
つくった作品を見学、2人3脚の作品です
来年はもっといろいろ工夫して作りましょう!





みなさん 来て良かった!すばらしかった!と感想を述べられました
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月15日
認知症予防10か条 第8条こまやかな気配り
認知症予防10か条
第8条 こまやかな気配りをしたよい付き合いを
相手の心に添い、細かい点まで優しい心づかいをして(理解と受容)、情緒的なゆるやかな信頼と平和な人間関係(なじみの心の結びつき)をもつことは、安心・安住の生き方に最も必要なものです。
そうでなく、自分本位で一方的、頑固で偏屈な態度での人への対応は、上下的な力関係の厳しい対人関係となり、対立的な支配・服従のような中で極端化すると、独りよがりや孤独(閉じこもり)となり、不安、不満、不信が多く、柔らかな人間関係が失いやすくなります。これによる心の困惑・混乱は、生き生きとした自主的な生き方を失わせ、知的な人柄や、活動の減弱、まとまりを欠き(解体)認知症化を促進したりします。
生きる頼りのよりどころ(生きがい)、特にその人との付き合い(コミュニケーション)は、好ましい人間性をはぐくみ、自由に知的能力を発揮できてぼけに対抗する健全な精神生活が維持できます。よく言われるように、「自分のまわりに、いつもよく話せる人が20人以上いるか」ということは、自らに振り返ってみる必要があります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
りの拠り所
第8条 こまやかな気配りをしたよい付き合いを
相手の心に添い、細かい点まで優しい心づかいをして(理解と受容)、情緒的なゆるやかな信頼と平和な人間関係(なじみの心の結びつき)をもつことは、安心・安住の生き方に最も必要なものです。
そうでなく、自分本位で一方的、頑固で偏屈な態度での人への対応は、上下的な力関係の厳しい対人関係となり、対立的な支配・服従のような中で極端化すると、独りよがりや孤独(閉じこもり)となり、不安、不満、不信が多く、柔らかな人間関係が失いやすくなります。これによる心の困惑・混乱は、生き生きとした自主的な生き方を失わせ、知的な人柄や、活動の減弱、まとまりを欠き(解体)認知症化を促進したりします。
生きる頼りのよりどころ(生きがい)、特にその人との付き合い(コミュニケーション)は、好ましい人間性をはぐくみ、自由に知的能力を発揮できてぼけに対抗する健全な精神生活が維持できます。よく言われるように、「自分のまわりに、いつもよく話せる人が20人以上いるか」ということは、自らに振り返ってみる必要があります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
りの拠り所
2009年10月14日
静岡第一テレビ取材の打合せ
だいいちテレビ報道局報道部富士支局記者
宮本 亜紀さんがリアルタイムしずおかの番組
10月28日の取材の打ち合わせに来訪しました。

とてもお若くておきれいでびっくり

18:20~18:26ごろの放送になりそうです。
日時が分かったらお知らせします。
是非皆さん見てください!!
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
タグ :静岡第一テレビ
2009年10月14日
2009年10月14日
認知症をよく理解するための8大法則 1原則 第8法則
認知症をよく理解するための
8大法則 1原則
(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師)
第8 法則 衰弱の進行に関する法則
「認知症の老化の速度は非常に速く、認知症のない人の約3倍のスピードで進行する」という特徴をいいます。認知症高齢者グループと正常高齢者グループのそれぞれ1年ごとの死亡率を5年間追跡した調査結果(聖マリアンナ医科大学長谷川和夫前理事長ら調査)、認知症高齢者の4年後の死亡率は83.2%で、正常高齢者グループの28.4%と比べると3倍になっていました。したがって何年何十年にわたって介護し続けなければならないのかと思い悩んでいる家族に対して、私は、次のように説明することにしています
「同じ年齢の正常な人と比べると、認知症の人の場合、老化が3倍のスピードで進むと考えてください。例えば、2年たてば6歳年をとったと同じ状態になりますから、6割位の人は認知症が出てから6~7年以内に死亡しています。見てあげられる期間は短いのです。」
介護に関する原則
「認知症の人が形成している世界を理解し、大切にする。その世界と現実とのギャップを、感じさせないようにする」。これが「介護に関する原則」です。私は認知症の人を介護する介護者に対して、「本人の感情や言動をまず受け入れて、それに合うシナリオを考え演じられる名優になってください。それが本人にとっても、あなたにとっても一番よい方法です。そして名優は時には悪役を演じなければなりませんよ」と話すことにしています。
認知症の人の世話をすることはときに大変辛く苦労が多いものです。介護者は家族の間で、あるいは経済的にも、また、社会に対しても、いろいろな問題を背負い込むものです。そんな場合も自分自身も俳優であると発想することは、心の負担をほんの少しでも軽くすることにもなるはずです。
とにかく認知症の人が、自分は周囲から認められているのだ、ここは安心して住めるところだ、と感じられるように日ごろから対応することが、一番楽で上手な介護になるのです。
「感情残像の法則」のところでも述べましたように一旦抱いた感情に関しては残像のように長い間残るので、認知症の人に良い感情をもってもらうことが介護のポイントになるのです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
8大法則 1原則
(認知症の人と家族の会 副代表 杉山孝博医師)
第8 法則 衰弱の進行に関する法則
「認知症の老化の速度は非常に速く、認知症のない人の約3倍のスピードで進行する」という特徴をいいます。認知症高齢者グループと正常高齢者グループのそれぞれ1年ごとの死亡率を5年間追跡した調査結果(聖マリアンナ医科大学長谷川和夫前理事長ら調査)、認知症高齢者の4年後の死亡率は83.2%で、正常高齢者グループの28.4%と比べると3倍になっていました。したがって何年何十年にわたって介護し続けなければならないのかと思い悩んでいる家族に対して、私は、次のように説明することにしています
「同じ年齢の正常な人と比べると、認知症の人の場合、老化が3倍のスピードで進むと考えてください。例えば、2年たてば6歳年をとったと同じ状態になりますから、6割位の人は認知症が出てから6~7年以内に死亡しています。見てあげられる期間は短いのです。」
介護に関する原則
「認知症の人が形成している世界を理解し、大切にする。その世界と現実とのギャップを、感じさせないようにする」。これが「介護に関する原則」です。私は認知症の人を介護する介護者に対して、「本人の感情や言動をまず受け入れて、それに合うシナリオを考え演じられる名優になってください。それが本人にとっても、あなたにとっても一番よい方法です。そして名優は時には悪役を演じなければなりませんよ」と話すことにしています。
認知症の人の世話をすることはときに大変辛く苦労が多いものです。介護者は家族の間で、あるいは経済的にも、また、社会に対しても、いろいろな問題を背負い込むものです。そんな場合も自分自身も俳優であると発想することは、心の負担をほんの少しでも軽くすることにもなるはずです。
とにかく認知症の人が、自分は周囲から認められているのだ、ここは安心して住めるところだ、と感じられるように日ごろから対応することが、一番楽で上手な介護になるのです。
「感情残像の法則」のところでも述べましたように一旦抱いた感情に関しては残像のように長い間残るので、認知症の人に良い感情をもってもらうことが介護のポイントになるのです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月13日
認知症の人と家族の会のつどいに参加
本日フィランセにおいて富士宮家族会のさくら会の皆さんと毎年恒例の
交流会を行ないました。認知症の人が買い物に行って困っていることを
テーマに各グループ6組6~7名集まり意見交換しました。10:30~14:00
実際に介護している方々からの生の声も聞くことができました。さくら会の皆様
有難うございました。こらからも意見交換会を宜しくお願いいたします。
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月13日
2009年10月13日
10/10(土)の朝日新聞に掲載されました☆

介護労働センターの内野さん http://ni2n3kyaku.i-ra.jp/e116491.html
早々にお電話ありがとうございます
内野さんの温かい励ましに、いつも癒されています

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月13日
Q&A 落ち着きのなさとイラつきに困っています
Q 43 アルツハイマー病の夫は突然、発作的に落ち着きがなくなります。このような時私はどうしたらよいか、途方に暮れてしまいます。なぜこのようになるのでしょうか、そして私はどのように対応したらよいのでしょうか?
A:2人3脚でもこのような利用者さんがおります。あまり頻繁に起こると周りの利用者さんも巻き込みトラブルになりかねませんし、スタッフもストレスが溜まってしまいます。私たちプロでさえ大変なのですから、さぞお困りののことでしょう。落ち着きのなさは、アルツハイマー病やレビー小体病、脳血管性認知症の利用者さんによくみかける症状です。あらかじめ避けることができるものもありますので参考にしてみてください。
突然、落ち着きがなくなってくるとき、それが苦痛や不快感から生じている可能性があります。歯痛は苦痛の一般的な原因ですから、歯は絶えず調べてもらい処置しておきましょう。また、消化不良や便秘のような消化器系の問題も、よく苦痛や不快感をもたらします。しかし、これも食事に気よつけていれば避けることができる場合があります。食物繊維の多いものやビタミン類の多く含んでいる果物や野菜を十分摂りましょう。
また、膀胱が尿でいっぱいになると、落ち着きがなくなる場合がとても多いのです。もし尿が出にくくなっているようでしたら、尿路感染症を起こしているかもしれません。または、前立腺肥大症のサインかもしれませんので、治療を受けてください
ご主人が飲んでいる薬は、どんなものでも落ち着きをなくさせる原因になりかねます。ですから、医師に相談して減らせる薬があるか、やめてよい薬があるかどうか、検討してもらうことが必要です。紅茶やコーヒーなどカフェインの強い飲み物も、落ち着きをなくさせたり、興奮状態を引き起こし、それらをいっそう悪化させます。
他にに考えられることとしては、退屈するから落ち着きがなくなる場合があります。2人3脚では、そういう時スタッフは、仕事探しを始めます。役割を持っていただくことで落ち着いてくる場合があります。ご主人にもそれまで以上の活動の場を見つけてあげるとよいでしょう。
突然落ち着きがなくなっても、散歩に連れ出したり、何か身体を使うことをさせてあげると症状がなくなる場合があります。認知症が進行するにつれコミュニケーションが困難になってきます。自分の言いたいことが言えなくなり、イライラする場合が多くなります。このようなことをしてもうまくいかないときには、ご主人が不安にかられ気が動転しているためかもしれません。そのようなときには何度も抱きしめてあげたり、しばらくの間ご主人のそばに寄り添って、手を握ったり、本を読んであげたリするとよいでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
A:2人3脚でもこのような利用者さんがおります。あまり頻繁に起こると周りの利用者さんも巻き込みトラブルになりかねませんし、スタッフもストレスが溜まってしまいます。私たちプロでさえ大変なのですから、さぞお困りののことでしょう。落ち着きのなさは、アルツハイマー病やレビー小体病、脳血管性認知症の利用者さんによくみかける症状です。あらかじめ避けることができるものもありますので参考にしてみてください。
突然、落ち着きがなくなってくるとき、それが苦痛や不快感から生じている可能性があります。歯痛は苦痛の一般的な原因ですから、歯は絶えず調べてもらい処置しておきましょう。また、消化不良や便秘のような消化器系の問題も、よく苦痛や不快感をもたらします。しかし、これも食事に気よつけていれば避けることができる場合があります。食物繊維の多いものやビタミン類の多く含んでいる果物や野菜を十分摂りましょう。
また、膀胱が尿でいっぱいになると、落ち着きがなくなる場合がとても多いのです。もし尿が出にくくなっているようでしたら、尿路感染症を起こしているかもしれません。または、前立腺肥大症のサインかもしれませんので、治療を受けてください
ご主人が飲んでいる薬は、どんなものでも落ち着きをなくさせる原因になりかねます。ですから、医師に相談して減らせる薬があるか、やめてよい薬があるかどうか、検討してもらうことが必要です。紅茶やコーヒーなどカフェインの強い飲み物も、落ち着きをなくさせたり、興奮状態を引き起こし、それらをいっそう悪化させます。
他にに考えられることとしては、退屈するから落ち着きがなくなる場合があります。2人3脚では、そういう時スタッフは、仕事探しを始めます。役割を持っていただくことで落ち着いてくる場合があります。ご主人にもそれまで以上の活動の場を見つけてあげるとよいでしょう。
突然落ち着きがなくなっても、散歩に連れ出したり、何か身体を使うことをさせてあげると症状がなくなる場合があります。認知症が進行するにつれコミュニケーションが困難になってきます。自分の言いたいことが言えなくなり、イライラする場合が多くなります。このようなことをしてもうまくいかないときには、ご主人が不安にかられ気が動転しているためかもしれません。そのようなときには何度も抱きしめてあげたり、しばらくの間ご主人のそばに寄り添って、手を握ったり、本を読んであげたリするとよいでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月12日
2人3脚の菜園

大根葉のおろ抜きをしています
おろぬいた大根葉は夕食のおひたしになります

エリザベスサンが丹精こめて育てています


絹さや、小かぶ、ブロッコリー、大根、油菜


今年のみかんは粒が大きいです
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月12日
サトイモの収穫

全部で37キロの収穫
ちび芋は本日のおやつです


皆さんできれいにひげを取ったのであっという間に出来上がり





セレベスも上手に出来ました
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月12日
認知症予防10か条 第7条 考えをまとめて表現する習慣を
認知症予防10か条
(認知症予防協会より)
第7条 考えをまとめて表現する習慣を
少しでも頭の衰えを防ぐためには、積極的に頭を使うことが必要です。しかし、その場合漠然と頭を使うのでは、あまり脳への刺激とはならず、活性化をもたらしません。
例えば、テレビのドラマや映画を見ても刺激を受けることになりますが、ただし字を追うだけではあまり頭を使うことにはなりません。その内容や感想、批評を自分で考え、まとめて表現することが、あれこれと頭を使うことになり、脳の活性化に役立つことになります。書物を読んで考えをまとめることはさらに良いです。
仕事を離れ、趣味として短歌や」俳句ををしているお年寄りは、自分で見たこと、感じたことを適切な短い言葉で表現していますが、上手に頭を使っていることになります。また、将棋や碁も頭を使うことでは脳の活性化に役立ちます。
認知症予防には、頭を使い、脳の神経細胞を刺激し活性を与えておくことであり、それには日ごろから何事も考え、それをまとめ表現する習慣を身につけておくことが大切です。例えば、毎日日記を書く、それも1日の出来事と感想をまとめて表現する、親戚や親しい友人に自分の近況を手紙に書いて出したり、読書の後には感想を書くことは誰にでも出来る認知症予防の1つです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
(認知症予防協会より)
第7条 考えをまとめて表現する習慣を
少しでも頭の衰えを防ぐためには、積極的に頭を使うことが必要です。しかし、その場合漠然と頭を使うのでは、あまり脳への刺激とはならず、活性化をもたらしません。
例えば、テレビのドラマや映画を見ても刺激を受けることになりますが、ただし字を追うだけではあまり頭を使うことにはなりません。その内容や感想、批評を自分で考え、まとめて表現することが、あれこれと頭を使うことになり、脳の活性化に役立つことになります。書物を読んで考えをまとめることはさらに良いです。
仕事を離れ、趣味として短歌や」俳句ををしているお年寄りは、自分で見たこと、感じたことを適切な短い言葉で表現していますが、上手に頭を使っていることになります。また、将棋や碁も頭を使うことでは脳の活性化に役立ちます。
認知症予防には、頭を使い、脳の神経細胞を刺激し活性を与えておくことであり、それには日ごろから何事も考え、それをまとめ表現する習慣を身につけておくことが大切です。例えば、毎日日記を書く、それも1日の出来事と感想をまとめて表現する、親戚や親しい友人に自分の近況を手紙に書いて出したり、読書の後には感想を書くことは誰にでも出来る認知症予防の1つです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月11日
家族介護者の心理 パート2
家族介護者の心理 パート2
( 認知症の人と家族の会 東京都支部 笹森貞子氏の一部より)
ステップ 2 拒絶期
介護者はせっかく気づき上げた我が家の生活リズムを守ろうと必死ですが、信じられないような老人の言動に振り回されストレスで一杯のことでしょう。介護者が嫁の場合は、結婚して嫁いでいる実の娘や親戚から好意とはいえ、色々な助言をされ混乱するのがこの時期なのです。なかには介護方法を学べとばかりに分厚い図書を送ってきたり、介護の支援もせず口だけ出す人もいます。それがまた、介護者の負担になりさらにストレスが溜まります。大変な思いの日々を送っている介護者にとってはどんなに理論的的に正しくても断定的に言われると感謝よりむしろ反感を覚えるものです。
介護者は孤立無援のような気持ちで介護を抱え込み被害者意識が強まり、介護に対して 否定的になってしまう場合があります。この時期は介護する家族、介護される老人にとって、とても辛い時期です。介護する家族は被害者意識が強く、逃げ腰となり、老人の辛さまで気づくゆとりがありません。このような時期はとくに介護者にとっては心の支えになる支援者が必要です。身内も介護に対する意見をいうより、介護者を支えるときです。介護支援ができなくても、ちょっとした言葉の気づかいが大きな支えになるときもあるのです。
この時期専門職の方には、介護者の辛い立場を十分受け止めていただき、共感受容していただきたいものです。「あなたの味方です」「どうぞ私に向かって愚痴をいっぱいはきだしてください」という気持ちで受け止めましょう。
ステップ 3 居直り期
「混乱」「拒絶」と通ってきた介護者自身、、多くのことを経験します。介護の現場に反発して逃げ出そうと考えたり、反省したりそれ以外の人間関係に悩んだり、色々な意味で介護の現実を知ってきました。経験から貴重なことを学び、認知症老人に対する理解も進み、それなりの対応の仕方も身につけました。そして1日1日が過ぎていきます。
介護者は「あんなに辛い思いをしながら介護を乗り切ってきた。これからも色々な場面で悩み奮闘するだろうが、あのときの苦しみを思えば今やっている介護は楽なものだこれからも頑張ってやるしかない!」「自然流でやれるだけやろう」というような心境になります。まさに居直りの境地です。
このように前向きな気持ちになり、周囲を見回して経験者の話を聞いたり、多くの人の協力を得ようという気持ちになります。
近所の人に認知症である身内の話を堂々と話すことができるようになり、協力をを依頼できるようになります。
介護者は複雑な悩み、迷いを抱えながらも結局ここまで到達したのです。介護を逃げずにここまで頑張ってきたという事実が、介護者の今後の介護の支えになるでしょう。常にプラス思考でくよくよせず、常に前向きな気持ちを持ち続けていこうという気持ちになります。
専門職の方には「ここまでよく頑張りましたね」「これからは自分の時間を持ちながら、自分にご褒美を上げる気持ちで休息の時間を持ちましょう」と伝えてほしいものです。専門職の評価は介護者の大きな心の支えになりますし、大きな力になります。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
( 認知症の人と家族の会 東京都支部 笹森貞子氏の一部より)
ステップ 2 拒絶期
介護者はせっかく気づき上げた我が家の生活リズムを守ろうと必死ですが、信じられないような老人の言動に振り回されストレスで一杯のことでしょう。介護者が嫁の場合は、結婚して嫁いでいる実の娘や親戚から好意とはいえ、色々な助言をされ混乱するのがこの時期なのです。なかには介護方法を学べとばかりに分厚い図書を送ってきたり、介護の支援もせず口だけ出す人もいます。それがまた、介護者の負担になりさらにストレスが溜まります。大変な思いの日々を送っている介護者にとってはどんなに理論的的に正しくても断定的に言われると感謝よりむしろ反感を覚えるものです。
介護者は孤立無援のような気持ちで介護を抱え込み被害者意識が強まり、介護に対して 否定的になってしまう場合があります。この時期は介護する家族、介護される老人にとって、とても辛い時期です。介護する家族は被害者意識が強く、逃げ腰となり、老人の辛さまで気づくゆとりがありません。このような時期はとくに介護者にとっては心の支えになる支援者が必要です。身内も介護に対する意見をいうより、介護者を支えるときです。介護支援ができなくても、ちょっとした言葉の気づかいが大きな支えになるときもあるのです。
この時期専門職の方には、介護者の辛い立場を十分受け止めていただき、共感受容していただきたいものです。「あなたの味方です」「どうぞ私に向かって愚痴をいっぱいはきだしてください」という気持ちで受け止めましょう。
ステップ 3 居直り期
「混乱」「拒絶」と通ってきた介護者自身、、多くのことを経験します。介護の現場に反発して逃げ出そうと考えたり、反省したりそれ以外の人間関係に悩んだり、色々な意味で介護の現実を知ってきました。経験から貴重なことを学び、認知症老人に対する理解も進み、それなりの対応の仕方も身につけました。そして1日1日が過ぎていきます。
介護者は「あんなに辛い思いをしながら介護を乗り切ってきた。これからも色々な場面で悩み奮闘するだろうが、あのときの苦しみを思えば今やっている介護は楽なものだこれからも頑張ってやるしかない!」「自然流でやれるだけやろう」というような心境になります。まさに居直りの境地です。
このように前向きな気持ちになり、周囲を見回して経験者の話を聞いたり、多くの人の協力を得ようという気持ちになります。
近所の人に認知症である身内の話を堂々と話すことができるようになり、協力をを依頼できるようになります。
介護者は複雑な悩み、迷いを抱えながらも結局ここまで到達したのです。介護を逃げずにここまで頑張ってきたという事実が、介護者の今後の介護の支えになるでしょう。常にプラス思考でくよくよせず、常に前向きな気持ちを持ち続けていこうという気持ちになります。
専門職の方には「ここまでよく頑張りましたね」「これからは自分の時間を持ちながら、自分にご褒美を上げる気持ちで休息の時間を持ちましょう」と伝えてほしいものです。専門職の評価は介護者の大きな心の支えになりますし、大きな力になります。
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月11日
家族介護者の心理について
家族介護者の心理 パート1
(認知症の人と家族の会 東京都支部代表笹森貞子氏のコメントの一部より)
2人3脚を開業して2年が経過しました、鷹岡病院での看護課長時代には体験できない利用者様の生き生きした笑顔が今の私の原動力かもしれません。今回は介護家族の苦悩の大変さをいつも身近に感じていますので、家族介護者のたどる心理についてお話します。
一昨日SBSの金スマで放映された南田洋子さんを介護する奮闘記をご覧になった方も多いと思います。色々なことを感じとり考えさせられました。
認知症老人を在宅で介護する家族介護者の心理について考えてみたいと思います。ほとんどの家族介護者は「混乱」「拒絶」「居直り」「受容」段階を通過するようです。認知症の看護を20年以上関わってきましたが、私もこの過程はは実感しています。その過程過程の中でどのように支援させいただくか、私のこれからの課題でもあります。一緒に学んで見ましょう!
ステップ 1 混乱期
多くの人は認知症老人を家庭でお世話するのは始めての経験です。身内の衰えに出会ったとき、それを認めたくない思い、そのような病気になってほしくない願い、さらに老人のこれからのこと、家族のいきさつの生活のことを考え、遂に感情的になったり落ち込んだり祖ます。
老人に対しても「しっかりしてほしい」と激しく関わったり、どちらかというと老人を追い詰めるような言動に出てしまうことが多いようです。今は老人性認知症をマスコミも取り上げて何かと情報も入りますし、認知症について学んでいる人もいます。冷静に受け止められる人もいますが、反面頭で理解していても現実とのギャップに悩み不安を増す人もいます。
混乱期では老人の衰えと、出会った時期の対応が大切です。家族も不安のあまり「ぼけたんじゃないの」「しっかりしてよ」などの声を掛ける人がいますが慎みたいものです。混乱している本人自身が今、一番辛い時期なのです。老人が逆に攻撃的になったりうつ的になったりします。このような早い時期にこそ受診が必要なのです。専門職の方に期待したいことは家族にきちんと認知症のことを教え、対応の仕方の基本を助言してほしいということです。少なくともよかれと思って自己流で逆の対応をしないようにしてほしいものです。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
(認知症の人と家族の会 東京都支部代表笹森貞子氏のコメントの一部より)
2人3脚を開業して2年が経過しました、鷹岡病院での看護課長時代には体験できない利用者様の生き生きした笑顔が今の私の原動力かもしれません。今回は介護家族の苦悩の大変さをいつも身近に感じていますので、家族介護者のたどる心理についてお話します。
一昨日SBSの金スマで放映された南田洋子さんを介護する奮闘記をご覧になった方も多いと思います。色々なことを感じとり考えさせられました。
認知症老人を在宅で介護する家族介護者の心理について考えてみたいと思います。ほとんどの家族介護者は「混乱」「拒絶」「居直り」「受容」段階を通過するようです。認知症の看護を20年以上関わってきましたが、私もこの過程はは実感しています。その過程過程の中でどのように支援させいただくか、私のこれからの課題でもあります。一緒に学んで見ましょう!
ステップ 1 混乱期
多くの人は認知症老人を家庭でお世話するのは始めての経験です。身内の衰えに出会ったとき、それを認めたくない思い、そのような病気になってほしくない願い、さらに老人のこれからのこと、家族のいきさつの生活のことを考え、遂に感情的になったり落ち込んだり祖ます。
老人に対しても「しっかりしてほしい」と激しく関わったり、どちらかというと老人を追い詰めるような言動に出てしまうことが多いようです。今は老人性認知症をマスコミも取り上げて何かと情報も入りますし、認知症について学んでいる人もいます。冷静に受け止められる人もいますが、反面頭で理解していても現実とのギャップに悩み不安を増す人もいます。
混乱期では老人の衰えと、出会った時期の対応が大切です。家族も不安のあまり「ぼけたんじゃないの」「しっかりしてよ」などの声を掛ける人がいますが慎みたいものです。混乱している本人自身が今、一番辛い時期なのです。老人が逆に攻撃的になったりうつ的になったりします。このような早い時期にこそ受診が必要なのです。専門職の方に期待したいことは家族にきちんと認知症のことを教え、対応の仕方の基本を助言してほしいということです。少なくともよかれと思って自己流で逆の対応をしないようにしてほしいものです。
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月10日
団塊創業塾OB会第11回定例交流会
本日の午後は団塊創業塾定例会に参加しました
とってもいい勉強になりました
色々な方と出会えたことが大きな収穫です
団塊創業塾の代表 原田和正氏より
グローモデルとコーチングにおけるタイムマネジメントについて教わりました
~如何にして目標を管理しそれに向けて時間を有効に使うか~
サン・テクニカル社長 大石定之氏(80歳)
楽しくビジネスを進めるためには“若さと健康”
定年後の楽しいビジネスを支えるアンチエイジング
や若さの秘訣について語っていただきました
トゥモローカレッジ代表 川辺剛氏
誕生から立ち上げまでを熱く語っていただきました
大前研一氏主催の起業支援ファンドからの企業支援
これってすごいんですよ!ビッグニュースです
トゥモローカレッジの旅英語講師小粥おさ美氏
旅するための英会話 体験型レッスンについて
語っていただきました
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月10日
認知症を理解するための8大法則 1原則 第7法則
認知症を理解するための
8大法則 1原則
(認知症の人と家族の会 副代表杉山孝博医師)
第7法則 症状の了解可能性に関する法則
老年期の知的低下の特性や、第1~第6法則でまとめたような認知症の特徴を考えれば、認知症の症状のほとんどは、認知症の人の立場に立ってみれば十分理解できるものである、という内容の法則です。
夜間不眠といって、夜間になると目を覚まして、家族、特に介護者の名前を呼んで起こすことがあります。家族にとっては大変な悩みとなります。どうしてこのようなことが起こるのか考えてみましょう。
認知症が始まると、時間や場所の見当がつかなくなる「見当識障害」が知的機能の低下の一面として出てきます。そうすると、今自分が寝ている所も分からなくなる。目を覚ますと、真っ暗でシーンとして誰もいない。認知症の人にとってみれば、自分がどこにいるのかわからなくなって、大変な恐怖感を覚えるわけです。
私たちが旅館に泊まって、夜中に目を覚ましたときのことを考えてみて下さい。自分の寝ているところがいつもの部屋と様子が違うので、誰れでも一瞬不安を感じます。ところが次の瞬間、旅館に泊まっていることを思い出して安心し、再び何事もなかったように眠るのです。もし、そのとき、いくら考えても自分がなぜここにいるのかがわからなかったらどうでしょう。「いったいなぜ、こんな知らないところにいるんだろう」「家族は自分を置き去りにして、どこかへ行ってしまったのではないか」「眠っている間に誘拐されて、ここに閉じ込められているのではないか」
さまざまな考えが次々と頭に浮かんできて、数分後にはひどい恐怖に襲われることになるでしょう。
そういうときに私たちはどうするかというと、誰もいなければ一番頼りになる人の名前を呼んで、その人が来てくれるまで呼び続けるでしょう。また、歩く自由があれば、あらゆる部屋を探し回って自分の知っている人がいないか、つまり夫や妻はいないか、子供はいないかと探し回るはずです。
認知症の人も、このような状態に置かれたのと全く同じ行動を示していると考えれば、そんなにおかしくないはずです。したがって夜間の徘徊をおさえるにどうすればよいかということは、認知症の人の気持ちになってみればよく分かります。まず、ここは自分の部屋だと分かるようにしてあげて恐怖感を和らげてあげることがポイントです。
そのコツには以下のようなことがあげられます。
部屋も老化も明るくしておく、めをさましたときに、いつも使っているタンスや衣類が分かるようにしておく、夜中でも手日やラジオを適切な音量でつけておく、家族の声や好きな歌など録音したテープを流すなどいろいろな音が聞こえるようにしておくなど。大事なことは、認知症のひとの恐怖感をいかにおさえるかということです。
(社)認知症の人と家族の会のベテラン介護者は、こういうケースで困ったときは、添い寝をしてあげ、目を覚ましたときには「大丈夫よ」と言って手を握ってあげるということをしていました。そうすると、それほどひどく騒がないで眠ってくれるし、自分もよく休めるという事でした。私たちも子どもの頃何年間も母親に添い寝をしてもらいながら眠りについたことを思い出せばよいでしょう。
ところで、認知症の人の言動を正しく了解する上では、過去の経験が現在の認知症の症状と深い関連をもっている場合も少なくないことを覚えておいて下さい。周囲の人は本人の生活歴・職業歴を詳しく知って、認知症の人の気持ちを理解するように勤めることが大切です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
8大法則 1原則
(認知症の人と家族の会 副代表杉山孝博医師)
第7法則 症状の了解可能性に関する法則
老年期の知的低下の特性や、第1~第6法則でまとめたような認知症の特徴を考えれば、認知症の症状のほとんどは、認知症の人の立場に立ってみれば十分理解できるものである、という内容の法則です。
夜間不眠といって、夜間になると目を覚まして、家族、特に介護者の名前を呼んで起こすことがあります。家族にとっては大変な悩みとなります。どうしてこのようなことが起こるのか考えてみましょう。
認知症が始まると、時間や場所の見当がつかなくなる「見当識障害」が知的機能の低下の一面として出てきます。そうすると、今自分が寝ている所も分からなくなる。目を覚ますと、真っ暗でシーンとして誰もいない。認知症の人にとってみれば、自分がどこにいるのかわからなくなって、大変な恐怖感を覚えるわけです。
私たちが旅館に泊まって、夜中に目を覚ましたときのことを考えてみて下さい。自分の寝ているところがいつもの部屋と様子が違うので、誰れでも一瞬不安を感じます。ところが次の瞬間、旅館に泊まっていることを思い出して安心し、再び何事もなかったように眠るのです。もし、そのとき、いくら考えても自分がなぜここにいるのかがわからなかったらどうでしょう。「いったいなぜ、こんな知らないところにいるんだろう」「家族は自分を置き去りにして、どこかへ行ってしまったのではないか」「眠っている間に誘拐されて、ここに閉じ込められているのではないか」
さまざまな考えが次々と頭に浮かんできて、数分後にはひどい恐怖に襲われることになるでしょう。
そういうときに私たちはどうするかというと、誰もいなければ一番頼りになる人の名前を呼んで、その人が来てくれるまで呼び続けるでしょう。また、歩く自由があれば、あらゆる部屋を探し回って自分の知っている人がいないか、つまり夫や妻はいないか、子供はいないかと探し回るはずです。
認知症の人も、このような状態に置かれたのと全く同じ行動を示していると考えれば、そんなにおかしくないはずです。したがって夜間の徘徊をおさえるにどうすればよいかということは、認知症の人の気持ちになってみればよく分かります。まず、ここは自分の部屋だと分かるようにしてあげて恐怖感を和らげてあげることがポイントです。
そのコツには以下のようなことがあげられます。
部屋も老化も明るくしておく、めをさましたときに、いつも使っているタンスや衣類が分かるようにしておく、夜中でも手日やラジオを適切な音量でつけておく、家族の声や好きな歌など録音したテープを流すなどいろいろな音が聞こえるようにしておくなど。大事なことは、認知症のひとの恐怖感をいかにおさえるかということです。
(社)認知症の人と家族の会のベテラン介護者は、こういうケースで困ったときは、添い寝をしてあげ、目を覚ましたときには「大丈夫よ」と言って手を握ってあげるということをしていました。そうすると、それほどひどく騒がないで眠ってくれるし、自分もよく休めるという事でした。私たちも子どもの頃何年間も母親に添い寝をしてもらいながら眠りについたことを思い出せばよいでしょう。
ところで、認知症の人の言動を正しく了解する上では、過去の経験が現在の認知症の症状と深い関連をもっている場合も少なくないことを覚えておいて下さい。周囲の人は本人の生活歴・職業歴を詳しく知って、認知症の人の気持ちを理解するように勤めることが大切です。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月09日
2009年10月09日
朝日新聞記者来訪

fーBizの小出宗昭氏の紹介で朝日新聞記者後藤遼太氏来訪
施設内の見学、レクの見学、石田のインタビューを行いました
利用者さんたちの笑顔を感じ取れていただけたでしょうか
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月09日
認知症予防10か条 第6条 興味と好奇心をもつように
認知症予防10か条
(財団法人認知症予防協会)
第6条 興味と好奇心をもつように
きおくのっ前段階には、除法の登録がまず行われます。この際に注意の集中と持続が必要になります。注意が散漫になっていると、新しいことを見聞しても、いわば上の空という状態で、情報が神経細胞に入ってこないことになります。そして情報の登録が正しくなされなければ判断も適切に行われませんので、ぼけの発症につながることになります。
興味というのは、楽しい、おもしろいということが背景にあります。また好奇心は未知のものを知りたい、あるいは探りたいという意欲があります。そして、興味も好奇心も前向きの積極的な注意の持続を必要とします。したがって、自分のライフスタイルに興味と好奇心をもっていることはぼけの防止につながるといってよいのです。
私達の心の体験として、没頭体験と見通し体験があります。
没頭体験とは、一つのことに熱中していく体験で、新しい技術を習得するときなどに経験します。
見通し体験とは、自分の現在の作業や行為がどのような結果を生むのかを推測するもので、これによって私たちは自分を客観視、必要ならば軌道の修正を行います。
しかし、見通し体験ばかり多くなって、没頭体験がなくなるのは考えものです。没頭体験には、なんといっても興味と好奇心がが必要な条件になります。興味やボランティア活動、あるいは社会参加は脳の活性化につながり、ぼけの予防に大切な役割を果たすことになるでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
(財団法人認知症予防協会)
第6条 興味と好奇心をもつように
きおくのっ前段階には、除法の登録がまず行われます。この際に注意の集中と持続が必要になります。注意が散漫になっていると、新しいことを見聞しても、いわば上の空という状態で、情報が神経細胞に入ってこないことになります。そして情報の登録が正しくなされなければ判断も適切に行われませんので、ぼけの発症につながることになります。
興味というのは、楽しい、おもしろいということが背景にあります。また好奇心は未知のものを知りたい、あるいは探りたいという意欲があります。そして、興味も好奇心も前向きの積極的な注意の持続を必要とします。したがって、自分のライフスタイルに興味と好奇心をもっていることはぼけの防止につながるといってよいのです。
私達の心の体験として、没頭体験と見通し体験があります。
没頭体験とは、一つのことに熱中していく体験で、新しい技術を習得するときなどに経験します。
見通し体験とは、自分の現在の作業や行為がどのような結果を生むのかを推測するもので、これによって私たちは自分を客観視、必要ならば軌道の修正を行います。
しかし、見通し体験ばかり多くなって、没頭体験がなくなるのは考えものです。没頭体験には、なんといっても興味と好奇心がが必要な条件になります。興味やボランティア活動、あるいは社会参加は脳の活性化につながり、ぼけの予防に大切な役割を果たすことになるでしょう。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月08日
富士商工会議所エコーレ例会に参加
富士パークホテル6階にてランチ
手作りの甘栗の渋皮煮は会員さんからの差し入れ
総勢40名近い会員さんの参加です
料理も旬のお野菜をふんだんに使っており
とっても美味しかったです。その後は1階にて例会と
美肌リンパフェイスマッサージ講座でオイルマッサージの
方法を教わりました。オイルだけでリンパマッサージするだけで
美肌効果を自分自身で作り出しします。お肌しっとり

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月08日
本日のレクはボーリング♪

今日の午後は皆でミニボウリングを行いました。
グループホーム対小規模多機能の対戦です。
大いに盛り上がりました。




↑
クリックしてね

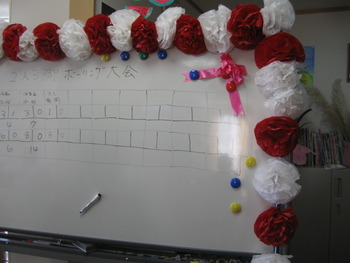
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月08日
「高福祉応分の負担」の考え方 提唱
「高福祉応分の負担」の考え方 提唱
認知症の人と家族の会リーフレットより
適正な要介護認定を求めるアピール
家族の会は07年秋に「提言私たちが期待する介護保険」を発表。厚生労働大臣に申し入れるとともに、認知症への対応も図られました。「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」報告(08年夏)に基づき、全国でのコールセンター(電話相談)、若年期認知症対策なども進もうとしています。
しかし、一方「非常識」と「家族の会」が批判する要介護認定方式の変更が打ち出されました。
このような状況を踏まえ、「家族の会」は新たに「提言2009年版}を発表しました。前回提言で主張した項目で実現したものを省き、新たな内容に改めました。
特に2009年版では、「高福祉応分の負担」という新しい考え方を提唱しています。これは社会保障のあり方は、」「高福祉高負担」でも「中福祉中負担」でも「低福祉低負担」でもなく、高福祉であって負担は誰でも納得できる負担であるべきという考え方です。
国の予算の考え方なども含めて財源論を議論する新しい概念として、提唱するものです。また、現在大きな問題となっている要介護認定についてのアピールも発表しました。さらに結成30周年及び公益社団法人移行申請を控えて、このたび「家族の会の理念」を制定しました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい

にほんブログ
認知症の人と家族の会リーフレットより
適正な要介護認定を求めるアピール
家族の会は07年秋に「提言私たちが期待する介護保険」を発表。厚生労働大臣に申し入れるとともに、認知症への対応も図られました。「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」報告(08年夏)に基づき、全国でのコールセンター(電話相談)、若年期認知症対策なども進もうとしています。
しかし、一方「非常識」と「家族の会」が批判する要介護認定方式の変更が打ち出されました。
このような状況を踏まえ、「家族の会」は新たに「提言2009年版}を発表しました。前回提言で主張した項目で実現したものを省き、新たな内容に改めました。
特に2009年版では、「高福祉応分の負担」という新しい考え方を提唱しています。これは社会保障のあり方は、」「高福祉高負担」でも「中福祉中負担」でも「低福祉低負担」でもなく、高福祉であって負担は誰でも納得できる負担であるべきという考え方です。
国の予算の考え方なども含めて財源論を議論する新しい概念として、提唱するものです。また、現在大きな問題となっている要介護認定についてのアピールも発表しました。さらに結成30周年及び公益社団法人移行申請を控えて、このたび「家族の会の理念」を制定しました。

にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ
2009年10月07日
富士市介護支援専門員(ケアマネージャー)研修会
本日フィランセにおいて富士市介護支援専門員第2回研修会に参加
19:00より「ケアマネジメント(介護現場)にぜひとも必要な新型インフルエンザ
を中心とした感染症対策」と題して木村内科医院副院長木村雅司先生よりお話
をお聞きしました。感染しない、感染させない取り組みが大切で感染したら7日間
は自宅療養しましょう。後半20:00からは各グループに分かれ医師との交流
を行ないました。私のグループは医師会の会長三村先生よりお話を伺いました。
にほんブログ村ランキング参加中!よかったらクリックして下さい
にほんブログ























